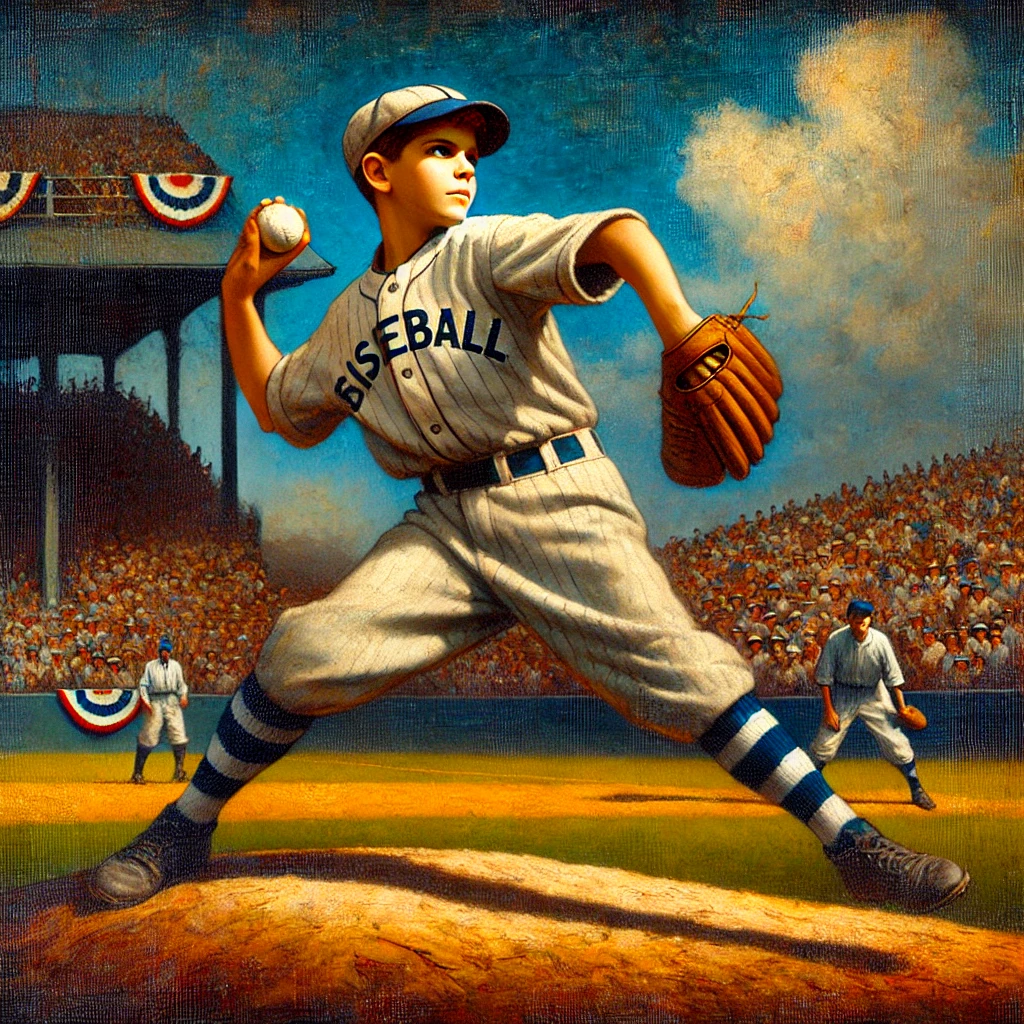「うちの子にもキャッチボールを教えたいけど、どう始めればいいのか不安…」そんなふうに感じていませんか?
特に小学校低学年や園児にとって、いきなりボールを投げ合う練習はケガや恐怖心につながることも。実は、全国優勝経験を持つ「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督も、「キャッチボールは順番が命」と語っています。
この記事では、低学年の子どもが無理なく、楽しくキャッチボールを学べる具体的な練習ステップや声かけのコツ、自宅でできるメニューまで丁寧に解説します。初めての一歩を、楽しく、安心して踏み出すために。
はじめに:低学年のキャッチボール指導で失敗しないために
小学校低学年の子どもにキャッチボールを教えるとき、多くの親御さんや指導者が「とりあえずボールを投げ合ってみよう」と始めてしまいがちです。しかし、実はこの「いきなりキャッチボール」は、子どもにとって大きな負担になりやすいのです。特に野球を始めたばかりの子どもにとって、正しい投げ方や捕り方が身についていない状態でボールを投げ合うことは、怪我や恐怖心の原因にもなります。
滋賀県の「多賀少年野球クラブ」は、全国大会で2018年、2019年と連続優勝を果たし、現在も全国の強豪チームとして知られています。このチームの辻正人監督は、特に初心者や低学年の子どもへの指導に時間をかけることで有名です。「キャッチボールは、正しい順序でステップを踏んで教える必要がある」と語る辻監督の方針は、多くの親御さんや指導者にとって学びになるでしょう。
親やコーチがよくやりがちな“いきなりキャッチボール”の危険性
「家でキャッチボールくらい、すぐできるでしょ」と思って、いきなりボールを投げてしまう。これは、非常にありがちなミスです。しかし、実際に子どもたちを指導している辻監督は、「いきなりキャッチボールをやらせないでください」と強く注意を促しています。なぜなら、初心者の子どもたちが恐怖心を抱いてしまうからです。
自分の顔や体に向かってくるボールに対して、防御反応が出るのは当然のこと。とくに体の正面で捕球しようとすると、ボールが顔に当たるリスクが高まり、怖さから野球自体を嫌いになってしまうケースもあります。「せっかく始めた野球なのに、最初の印象が“怖い”になってしまっては本末転倒です」と辻監督は語ります。
まずは子どもが“安全に・楽しく”野球と向き合えるよう、キャッチボールに入る前の準備段階が非常に重要なのです。
「多賀少年野球クラブ」の実例に学ぶ正しいアプローチ
全国大会での優勝経験を持ち、楽天のエース・則本昂大投手をOBに持つ「多賀少年野球クラブ」。その強さの根底には、“低学年・初心者指導にかける時間の多さ”があります。
辻正人監督は、「小学校5、6年生にはもう基本が入っているので、自分たちで考えて練習できます。一方、初心者に基礎を教えるのが監督の役目です」と語ります。つまり、指導の土台を作るのが幼少期の指導であり、ここを丁寧に積み上げているからこそ、クラブの強さが継続しているのです。
そのために、辻監督はまず「投げる」「捕る」という動作を分けて教えるところから始めます。いきなりキャッチボールではなく、投げ方の動作確認、捕り方の基礎をしっかりとステップごとに指導します。この“順序”が、子どもにとって無理なく野球を楽しめるポイントなのです。
ステップ①:まず「投げ方」だけを教える
キャッチボールと聞くと、「投げる」「捕る」を同時に練習するものだと思われがちですが、低学年の初心者にとってはそれが大きな負担になります。辻監督の指導法では、「まずは投げることだけに集中する」ことから始めます。これは、動作をシンプルにし、子どもが混乱しないようにするためです。
特に右利きの子どもには、「右手でボールを持って、頭の後ろへ、ステップステップ、ドーンと投げる」と、リズムをつけたシンプルな説明を使っています。このように分かりやすく、真似しやすい言葉で指導することが、投げ方の定着に非常に効果的なのです。
初心者には「投げる動作」を分解して教えるべし
「投げる」という動作は、一見単純に見えて、実は体全体の使い方が必要な複雑な運動です。腕の使い方だけでなく、ステップの踏み方、タイミング、リリースの位置など、細かな要素がたくさん含まれています。
そのため、辻監督は子どもたちに「投げる」動作を段階的に教えていきます。たとえば、ボールを持った手をまず耳の横まで上げる。そのまま前にステップを踏んで、最後にまっすぐリリース。このように、動作を細かく区切って指導することで、子どもたちも混乱せずに自然とフォームを身につけていくことができます。
ここで大切なのは、一度に全部教えようとしないこと。ひとつひとつの動作をしっかり理解させてから次へ進むことが、正しいフォームへの近道です。
「右手で持って、頭、ステップステップ、ドーン」辻監督の声かけ術
辻監督が実際に子どもたちに伝えているフレーズがあります。それが、「右手でボールを持って、頭、ステップステップ、ドーン」。とても簡単で、子どもにもリズムよく覚えられる声かけです。
このようなテンポのある言葉を使うことで、子どもはまるで遊びのような感覚で動作を身につけていきます。言葉がけには正確なフォームを意識させるだけでなく、「やってみたい」「できた」という意欲や達成感を引き出す力があります。
また、子どもが上手くできたときには、すかさず「今の最高!」「バッチリだね!」と声をかけることで、自己肯定感も育ちます。こうした声かけの工夫が、低学年指導の中では非常に重要です。
子どもが楽しくなる「成功体験」を与える声かけ例
低学年の子どもたちにとって、野球を「楽しい」と感じられるかどうかは、初期の成功体験が大きく関係しています。辻監督は、子どもが少しでも上手くできたときに、「今のは完璧だよ!」「すごい!その投げ方、プロみたい!」と声をかけます。
このように“できたこと”に注目して褒めることで、子どもは自信を持ち、次もまた頑張ろうという気持ちになります。逆に、ミスやできないことを指摘するだけでは、やる気をなくしてしまうこともあります。
大切なのは、「褒めるポイントを見つける目」と「すぐにフィードバックする姿勢」です。たとえ完璧でなくても、「前より良くなってるね」「そのステップがすごく上手だったよ」と具体的に声をかけてあげると、子どもはどんどん前向きになっていきます。
指導とは、技術だけでなく“心を育てる”ことでもあります。キャッチボールの指導は、その最初の一歩として、非常に重要な意味を持っているのです。
ステップ②:「捕り方」は怖がらせないことが最優先
キャッチボールにおいて「投げる」よりも難しいと感じる子が多いのが「捕る」動作です。特に低学年や初心者の子どもたちは、自分に向かって飛んでくるボールを本能的に怖がります。この「怖い」という感情が一度でも芽生えてしまうと、その後の野球の練習に対する意欲や集中力にも大きく影響してしまいます。
滋賀県の名門「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督も、「体の正面で捕らせようとすると、顔に当たってしまって子どもが怖くなります。最初はよけながら横でキャッチさせる方が良いんです」と語っています。まずは“怖くない”“できた!”という体験を積ませることが、子どもにとっての大きな一歩になります。
正面キャッチNG!横でキャッチする練習法
一般的には、キャッチボールでは体の正面で捕球することが理想とされていますが、これはある程度経験を積んだ子どもに対しての話です。野球を始めたばかりの低学年の子にいきなりそれを求めるのは、かなりハードルが高くなってしまいます。
辻監督は「まずは正面で捕るのではなく、体の横でボールをキャッチする練習から始めるべき」と話しています。たとえば、やや左(または右)からやってくるボールを“よけながら捕る”ことで、子どもは安全な距離感でボールに慣れていけます。この段階で「怖くない」と感じられると、自然とボールへの反応もよくなり、次のステップにスムーズに進むことができます。
また、無理に正面で捕るよう指導すると、失敗してボールが顔や体に当たる可能性も高くなり、それがトラウマになるケースもあります。最初は「横で捕ってもいいんだよ」と安心感を与えることが大切です。
柔らかいボール+段階的なステップアップが鍵
捕球の練習を行う際に、使用するボールの種類にも注意が必要です。辻監督が実際に使用しているのは、やわらかい素材の練習用ボールです。これにより、万が一キャッチに失敗して体に当たってしまっても痛みが少なく、子どもが怖がらずに練習を継続できます。
また、練習の進め方も重要です。いきなり飛んできたボールを捕らせるのではなく、まずは子どもがグラブを構えている場所に、下からゆっくりと柔らかいボールを投げ入れるところからスタートします。その後、徐々に距離や高さを加えていくことで、自然と捕球の技術が身についていきます。
段階的なステップアップにより、子ども自身が「できた!」という感覚を得ながら上達していくのが理想です。この“成功体験”が繰り返されることで、練習に対する前向きな気持ちも育まれていきます。
地面のボール拾いからスタートする理由
いきなり空中にあるボールを捕らせようとすると、初心者の子どもにとっては難しすぎて混乱してしまいます。そのため辻監督が導入しているのが、「地面のボールを拾う」という最もシンプルな動作からスタートする方法です。
これは、まず“グラブを正しく使う感覚”を身につけさせるためにとても効果的です。子どもたちは、自分のタイミングでボールに近づき、ゆっくりと拾うことができるため、恐怖心を感じずに練習を進められます。また、ボールを手にする動作の繰り返しが、自然とグラブ操作や手首の動きを学ぶきっかけにもなります。
この練習法は、野球の基本中の基本ではありますが、意外と見落とされがちな重要なステップでもあります。焦らず、楽しみながら“道具を使ってボールを扱う感覚”を育てていくことが、長い目で見たときの大きな成長につながります。
4. ステップ③:「フライ捕球」は空間認知能力のトレーニング
低学年の子どもにとって、フライ(上から落ちてくるボール)を捕ることは簡単ではありません。それでも、辻監督はフライ捕球の練習を“早い段階で取り入れるべき”と考えています。その理由は、フライを捕るためには空間認知能力が求められ、この力がつくと打撃や守備のレベルも大きく上がるからです。
つまり、フライ捕球の練習は「捕る技術」を高めるだけでなく、野球というスポーツそのものへの理解力と対応力を育てる、非常に有効なトレーニングになります。ただし、ここでもやはり“怖がらせないこと”が前提になります。
最初は“よけながら”でOK!フライ練習の工夫
初めてフライを捕る子どもに、いきなり頭上からボールを落とすと、「怖い!」「無理!」となってしまいます。そのため、辻監督は「最初は体の横で、よけながらキャッチさせています」と語っています。つまり、“正確に捕れなくてもいい、まずは落ちてくるボールに慣れる”ことが大切なのです。
使用するボールも、もちろん柔らかいもの。マシンや手投げでフライを上げ、少しずつ距離や高さを調整しながら、子どもに「キャッチできそう」という感覚を育てていきます。このように段階的にレベルを上げていくことで、恐怖心を抑えながらフライへの対応力を高めることができます。
怖がっているうちは、うまくいかなくても当然。まずは「見て動く」「動いてよける」ことからスタートしてOKです。
フライキャッチが打撃力につながる理由とは?
フライを捕る練習は、実は守備だけでなく「打撃力の向上」にもつながっています。辻監督によれば、フライを捕球できるようになるには、“落ちてくるボールの軌道を瞬時に判断し、体をどう動かすか”という空間認知能力が必要になります。この能力は、実は打撃においても非常に重要なのです。
打撃では、ピッチャーが投げたボールのスピードや高さ、変化を見極め、最適なスイングタイミングをとる必要があります。フライ捕球のトレーニングで視覚と動作の連動が鍛えられることで、結果的に打撃時の対応力も上がってくるのです。
また、「フライを捕れるようになった!」という成功体験が、守備への自信だけでなく、野球全体へのモチベーションにもつながります。楽しみながら感覚を磨いていくこの練習は、低学年の子どもにとってとても有効な成長機会となるでしょう。
自宅でもできる!低学年向けキャッチボール練習メニュー
少年野球を始めたばかりの子どもにとって、自宅での練習時間はとても大切です。ただし、「キャッチボール=公園やグラウンドでやるもの」というイメージが強く、家庭内での取り組みが難しいと思われがちです。でも実は、工夫次第で室内や庭先でも十分にキャッチボールの基礎を身につけることができるんです。
辻正人監督が率いる「多賀少年野球クラブ」では、初心者への指導において“いきなりキャッチボール”を避け、「まずは投げ方や捕り方を段階的に練習する」ことを重視しています。その考え方を自宅でも応用すれば、園児から小学生まで、無理なく楽しく練習が可能です。
親子で楽しく安全に取り組むための道具と環境
まず、自宅で安全に練習するためには、道具選びと練習環境が非常に重要です。辻監督が推奨するように、最初のうちは柔らかいボールを使うのが基本です。スポンジボールやウレタン素材のキャッチボール用ボールは、万が一当たっても痛みが少ないので、怖がらずに練習を続けることができます。
また、狭いスペースでも使える軽量のグラブ(特に子ども用のミット)や、グラブを使わずに素手でボールを拾う練習も、基本動作を学ぶにはとても効果的です。さらに、フロアマットやカーペットを敷くなどして、転倒や衝突のリスクを減らす工夫も忘れずに行いましょう。
親子で一緒に楽しみながら行うことが、子どもにとっての一番のモチベーションになります。「できたね!」「上手くなってきたよ!」という声かけひとつで、練習はぐっと前向きなものになります。
園児でもできる練習ステップ3選(動画紹介・リンク可能)
辻監督の指導をヒントにした、自宅でもできる3つの練習ステップをご紹介します。いずれも短時間で取り組めるので、飽きずに続けやすいメニューです。
① 地面のボール拾い練習(グラブ操作の基礎)
柔らかいボールを床に転がし、それをグラブまたは素手で拾う練習です。しゃがんで拾う動作を繰り返すことで、ボールへのアプローチや目の使い方を自然に学ぶことができます。
② キャッチごっこ(ゆっくり下から投げる)
子どもが構えたところへ、親が下からゆっくりと柔らかいボールを投げます。キャッチできなくても構いません。「グラブに当たったね!」など、少しの成功をたくさん褒めてあげることが大切です。
③ フライっぽいボール遊び(空間認知の練習)
やや高く投げた柔らかいボールを、子どもが“よけながら”キャッチする遊びです。正面で捕るのではなく、横や後ろに動いてボールを取る感覚を養います。最初はキャッチできなくても、「ボールを見て動けたらOK!」くらいのゆるい目標で始めましょう。
※動画紹介や外部リンクも可能ですので、ご希望があれば該当する練習例を動画付きでご案内できます。
おわりに:キャッチボールは「上手さ」より「楽しさ」が大事
少年野球を始めたばかりの子どもにとって、キャッチボールは“できるようになること”ももちろん大事ですが、それ以上に「楽しい」「またやりたい」と思えることの方が、はるかに大切です。最初から完璧を目指すのではなく、少しずつ成長を実感しながら前向きに取り組むことこそが、子どもの心と技術を大きく育ててくれます。
辻監督も、「野球の楽しさを知った子どもは、驚くほどのスピードで成長します」と話しています。その最初の入口が、キャッチボールです。だからこそ、焦らず、怒らず、そしてたくさん褒めながら進めることが一番のポイントなのです。
6-1. 子どもが野球を好きになる指導とは
「できないことを責める」のではなく、「できたことを一緒に喜ぶ」——これが、低学年の子どもたちにとって最良の指導法です。辻監督は、どんなに小さな進歩でも見逃さず、「今のいいね」「バッチリだったよ!」と声をかけています。このような前向きなフィードバックがあることで、子どもたちはどんどんチャレンジ精神を持ち、自ら考えてプレーするようになります。
また、最初のうちは親が一緒に取り組む姿勢も大切です。子どもは大好きな人と一緒にやるだけで楽しくなり、その時間が“野球=楽しい”という記憶として刻まれていきます。
全国トップチームも実践する「基礎重視」の強さの理由
全国トップクラスの「多賀少年野球クラブ」がなぜ強いのか——その答えは、技術や才能だけではありません。「初心者指導に最も時間をかけている」ことが、その強さの原点なのです。
投げ方と捕り方を分けて教える、正しい順番を守る、怖がらせない工夫をする。こうした基本に忠実な指導こそが、選手たちの土台を築き、やがて自ら考えて動ける力に変わっていきます。全国大会を制するようなチームでさえ、基礎を何よりも大切にしているという事実は、私たちが低学年の子どもたちに接するうえでの大きなヒントになるはずです。
だからこそ、焦らず、確実に。そして何より、子どもたちの「楽しい!」を育てながら進めていきましょう。キャッチボールは、その第一歩にふさわしい最高の時間です。